
受験生、もしくは早いと高校2年生の夏休みが過ぎたくらいから、だんだん志望校のことを具体的に意識し始める頃でしょう。
例えば国公立大学、志望大学&学部まで希望が決まっている、医学部や歯学部、薬学部など、選択肢に困らない場合は志望校選びは、さほど苦労しません。
とくに医系の場合、受験できる大学が限られてきますので、場合によってはライバルの友人と日程がまったくかぶるなんてことも。
試験会場で偶然あったら、お互いのためにあまり多くはお話ししないでおきましょう。
志望校選びで特に難しいのは私立大学
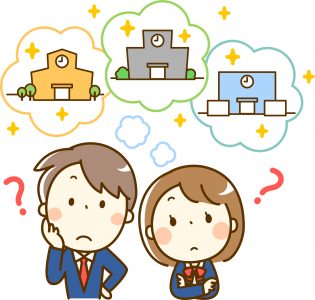
特殊な分野でもない限り、大学や学部はいっぱいありますから、受験校をどのように決めたらよいのか迷いますよね。
卒業生は1度、高校時代に受験していますから同じ大学を再度チャレンジしたり、さらに志望校をステップアップしたいという意欲のある方もいらっしゃるでしょう。
最終的な判断は受験指導の先生と、偏差値などを確認しながら決定します。
その前に、志望校を聞かれる前に自分なりに決めておきたい場合、そこで志望校を選ぶ時の基本は「何を優先するか」ですね。
「絶対にココしか行きたくない!」
という受験生もいれば、
「MARCHならどこでもいい」
とか、
「機械関係の勉強が出来るところ」
など、人によって様々。
あなたが何を優先したいのかを、まずははっきりしておきましょう。
大学名が最優先
行きたい大学の学部を複数受ける
例)「早稲田に行きたい。早稲田大学ならどこの学部でもいい。」
早稲田大学 法学部
早稲田大学 政経学部 政治
早稲田大学 商学部
早稲田大学 社会学部
このように、私立大学は理系文系それぞれの中で学部が複数あり、日程がかぶりませんから本命学部・抑え学部など、複数受験するパターンがあります。
学部が最優先
行きたい学部で日にち順に受ける
例)「経済学部で勉強したいから、経済学部のある大学から決めたい。」
立教大学 経済学部
中央大学 経済学部
成蹊大学 経済学部
日程がかぶる場合は経営、商などでも良いという方は多いですね。
その後、学力の伸び次第で難易度、通学条件(自宅に近いなど) でさらに絞っていきます。
ランクが最優先
早慶・MARCH・日東駒専などのレベルの近い枠で受ける
例)「早慶は難しいけど、日東駒専は楽に受かるレベルだから、MARCHならどこでも良い」
明治大学 理工学部
立教大学 理工学部
中央大学 理工学部
その中でよりどの学部を受けたいか、日程は厳しくないか検討。
※最近では「GMARCH」(MARCH+学習院)という呼び方もありますが、すべてひっくるめた広い範囲で用いることが多いです。
他にも志望大学の選び方があります。
国公立早慶 / 私立医学部 早慶理系
いわゆる難関大トップレベルなら、国公立私立、学部関係なく併願して受ける場合や、私立医学部受験生が早慶の理系も併願で受けるという場合などがあります。
入試問題の形式
非常にまれな例になってきますが、受験生の中にはマークセンス方式で中くらい程度までの難易度の問題なら高得点をとるのが得意だという方、難解な記述や説明、論証など、発想力を問う問題を2/3くらい解けるという方など、タイプがあります
両方得意な場合は良いですが、どちらか一方の極端な場合は問題形式に自分が合っている大学や学部が優先になりますね。
志望校選びのパターンは色々

実家から通いたいとか、東京の交通の便がいい大学とか、人数が多い大学、就職先など志望動機は複数の条件が色々と重なって最終的に決定されます。
とにもかくにも学校で調査書を書いてもらうまでは志望校選びに気をとられず、しっかりと学力を伸ばしてください。








